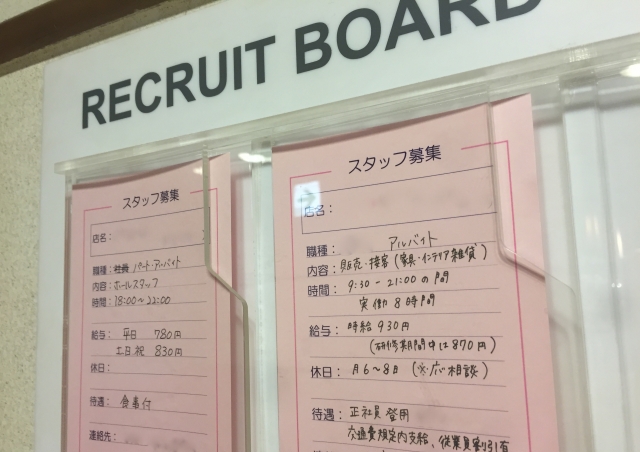
少子高齢化の進展、いわゆる団塊世代の退職等により、新卒一括採用と終身雇用という我が国の雇用慣行が崩れ始め、人材不足が叫ばれるようになって久しい。近時、このような人材不足への対応として、中途採用の拡大や、スキマバイトの利用等が広がっているが、なお人材不足の解消には不十分な状況である。
トランプ関税に端を発する関税戦争の中、今後の景気の不透明感も否めないが、人材(人財)なくしては、このような混迷する世界で競争を勝ち抜くことができないことを疑う余地はない。
人材を集めるノウハウは、人材紹介業者や人材派遣業者等、人材確保のプロフェッショナルが有するところではあるものの、以下では、人材不足に悩む事業者の方々が自ら人材を募集し、人材を確保するための方策を考えてみたい。
1 雇用のミスマッチへの対応策
まず、人材を募集しているが、欲しい人材を採用することができないという事業者の悩みについて考えてみる。
(1)欲しい人材が採用できないのは、そもそも人材の応募がないか、欲しい人材の応募がないかのいずれかである。
前者の人材の応募がないのは、いうまでもないが、募集の際に示している待遇(給与、各種手当、退職金、勤務場所、業務内容、所定労働時間、休日、転勤の有無等)が悪いためであり、待遇を改善するのが王道の対応策である。
しかし、給与や各種手当等の金銭面での待遇改善は、既存の従業員との待遇の逆転や既存の従業員の不満を招きかねず、その解消のためには既存の従業員の給与や各種手当等の改善といった大幅なコストアップが必要となる。大企業や業績・財務の好調な事業者であれば多少のコストアップはさほど大きな問題ではないかもしれないが、それ以外の事業者にとっては、コストアップになるような対応を採ることは容易ではない。
もっとも、最近では、新型コロナウイルス感染症の蔓延時に一時的にリモートワークが広がったことの影響もあったのか、給与や各種手当といった金銭面での待遇の重要性が低下している。むしろ、特に若年層を中心に、やりがい、リモートワークの許容、休日の多さ等といった非金銭面での待遇の重要性が増しつつある。こういった非金銭面での待遇の改善は、さほどコストがかかる訳でもなく、既存の従業員の金銭面での待遇改善を図る必要もないため、有効かつ合理的である。
(2)これに対し、欲しい人材の応募がないというのは、事業者側が、応募者の経歴、経験、年齢等から、採用に至らない場合である。
この場合は、やはり待遇を改善して希望するような経歴、経験、年齢等の応募が来るよう努めることが常道であるが、給与等のコストを伴う待遇改善が難しいのであれば、希望条件のいずれかについて譲歩せざるを得ない。例えば、経歴や経験を重視するのであれば、年齢は譲歩しても良いのではないだろうか。経歴や経験があれば、「育てる」必要がないため、50歳や60歳を超えていても活用の可能性は十分に見込める。特に、人数に厚みがある団塊ジュニア世代も50歳を超えつつあるが、この年齢層は、大企業で早期希望退職が行われやすく、優秀な人材が供給される可能性もあるため、少なくともこれから数年間は、50歳以上の人材の活用も真剣に検討されても良いのではないだろうか。
実際、50歳以上の人材の活用は広がりつつあり、今後こういった年齢層の人材も取り合いになる可能性も否定できないため、早期の対応をお勧めしたい。
2 早期離職の防止
次に、弁護士法との抵触が懸念される退職代行業者まで登場する等、新規学卒者の早期離職が話題となっているが、これに限らず、終始雇用の崩壊や中途採用の拡大等で労働市場が流動化しており、解雇や定年退職によらない離職による人材流出にお悩みの事業者も少なくない。
以下では、このような離職による人材流出を防止するといういわば裏からの人材確保のあり方について検討する。
(1)王道の離職防止策
王道の離職防止策は、やはり、金銭面での待遇の改善である。しかし、金銭面での待遇の改善によって従業員に一旦離職を思いとどまらせることができたとしても、他の事業者が同様に金銭面での待遇を改善すれば、従業員の離職熱が高まることは避けられない。そのため、金銭面での待遇改善によって離職を防止するためには、改善を継続していくことが必要不可欠であり、人件費の増大を必然的に伴うこととなることには注意が必要である。
もっとも、大企業については、労働分配率を低く抑え、有事のために内部留保を蓄えてきた以上、たとえ少々人件費が増大しても、さほど大きな問題ではない(上場会社においては、従業員の賃金の増額改定を発表しても、株価が下がることは少なく、むしろ成長への自信の表れとして、市場からは積極的な評価につながる傾向が強まっている。)。
(2)非金銭面での待遇改善
次に、非金銭面での待遇改善による離職防止策の一部を取り上げる。
ア 週休3日制
一部の大企業において、(試験的に)週休3日制が導入されているようであるが(その導入によって事業者側の収益にどのような効果があるのか否かはここでは立ち入らない。)、これには色々な形態が考えられる。
大まかにいうと、1つ目は、週休3日制によって単純に1週間当たりの労働時間が減少させて給与を減額するというパターン、2つ目が給与を維持するために1日当たりの労働時間を増やすというパターン、3つ目が労働時間を減らしたまま給与も減らさないパターンとなる。
いずれの場合も就業規則の改正は不可欠であるが、いうまでもなく、離職防止の効果が最も高いのは3つ目のパターンである。しかし、このパターンは、特に労働集約型の事業者は、労務に従事する従業員が減るにもかかわらず人件費が変わらないため、少なくとも全面的に実施することには相当な困難を伴うことになる。
また、2つ目のパターンは、時間外労働手当の支払が必要となるため、事業者にとってあまり魅力的な選択肢とはいえないと思われる。
他方、1つ目のパターンは、実現のハードルが最も低いとはいえるが、育児や介護といった事情のある従業員でもない限り、さほど離職防止策として高い効果は期待できないおそれがある。また、単純に労務に従事する従業員が減ることへの対応も不可欠となる。
現実的には、育児や介護といった事情のある従業員に1つ目のパターンを選択できるものとし、また週休2日制への復帰も自由に選択できるようにしつつ、余裕があれば3つ目のパターンを目指していくということになろう。
イ 1日当たり労働時間の短縮
1日当たり労働時間を短縮する手法にも、給与を減額するパターンと減額しないパターンの2つが考えられる。
この場合も就業規則の改正は不可欠であるが、離職防止の効果が高いのは、当然、給与を減額しないパターンである。1日当たり労働時間の短縮は、その短縮幅が小さくすれば、週休3日制より実現へのハードルが低いとはいえるものの、小幅な短縮では、離職防止の効果が小さくなると思われる。
他方、給与を減額するパターンであるが、大幅な労働時間の短縮幅に比して給与の減額幅を小さくするような場合でもない限り、離職防止の効果はほぼ期待できないと思われる。なお、労働時間の短縮幅よりも給与の減額幅を大きくすることは、不利益変更に当たり、許されない。
ウ フレックスタイム制の導入
また、フレックスタイム制の導入も考えられるが、結局コアタイムの就労が必要となるため、リモートワークも併用しなければ、離職防止策としてはさほどの効果は期待できないと思われる。
なお、フレックスタイム制の詳細については、厚生労働省のホームページ「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000380237.pdf)を参考にされたい。
(3)ジョブディスクリプション(職務記述書)の功罪
ところで、最近では、ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成が叫ばれている。ジョブディスクリプションは、求職者や従業員が自己のスキルを可視化するものとして極めて有用である。他方、大企業、特に上場企業においては、非財務情報情報として「人材育成方針」や「社内環境整備方針」の開示が義務化された上、スキルマップを作成して人材スキルを可視化することで、従業員や求職者のスキルと業務とのマッチングを図ることもできるため、業務内容のミスマッチによる離職を防止できるという大きな利点があるとされている。
しかし、人的資本の開示が義務化されておらず、またスキルマップを作成する余裕がない事業者にとって、従業員や求職者がジョブディスクリプションを作成することにメリットがあるだろうか。
そもそも、スキルマップもない事業者が、ジョブディスクリプションを有する従業員や求職者が求める業務へ的確に就かせることができるかどうかは疑問である。むしろ、ジョブディスクリプションによって自己の有するスキルを的確に把握した従業員や求職者は、転職に積極的で、かつ容易に転職できる可能性が高い。そうすると、スキルマップを作成する等して部署ごとに求められるスキルを把握している事業者でもない限り、ジョブディスクリプションを有する従業員を引き留めることは困難であろう。
終身雇用が完全に崩壊し、ジョブディスクリプションが広く活用され、大半の事業者がスキルマップを作成するような時代になった場合は別として、少なくとも現時点では、事業者が積極的にジョブディスクリプションの作成を奨励する必要はないと思われる。
このように、少なくとも現時点では、ごく一部の事業者を除き、ジョブディスクリプション作成を奨励することは、人材確保どころか、離職を促進することになりかねない。
3 さいごに
以上、ごく一部であるが、人材(人財)不足への対応策を検討した。
事業者の皆様におかれては、労働環境の改善、公平な人事評価システムの導入、研修の充実、福利厚生の充実、定年延長、リファラル採用等、様々な形で人材確保に日々努力されていることと思われるが、以上で検討した対応策がその一助になれば望外の喜びである。
なお、今回の検討においては、人材不足への対応策にスポットを当てたため、各対応策の法的リスクについてはごく一部に触れたにとどまる。それぞれの対応策の実施を検討するに当たっては、弁護士等に相談されることをお勧めする。
以 上
※本トピック掲載の記事につきましては、転載自由となっております。
転載された場合、転載先のサイト様を紹介させて頂きますので、是非ご連絡いただければと存じます。
この弁護士に相談が出来る、智進ダイレクトへ
